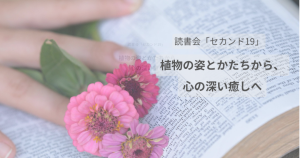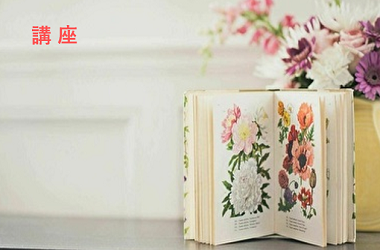英国の田園風景を形づくってきたのは、
イングリッシュ・エルム
(ヨーロッパニレ)でした。
ローマ時代に
イタリアから英国にもたらされ、
街路樹として道を守り、
屋敷林として風をやわらげ、
木材は農具や家具、
船や車軸に使われました。
丈夫でねばりがあり、
乾燥にも強く、
人の手によって活かされ、
暮らしを支えてきた木。
そのしなやかな強さは、
長い年月を通じて
人々の生活に息づいてきました。

けれど、エルムは
ケルトの守護樹には
結びつけられていません。
神聖な木というより、
日々の暮らしに寄り添う、
身近な木だったようです。
ローマでは、エルムは
伝達と旅の神マーキュリーと
結びつけられました。
人々は、ブドウの蔓を
エルムに絡ませて育てることから、
「支えながら実りをもたらす」
橋渡しの力を
見出していたのかもしれません。
一方、北欧の神話では、
神々が最初の人間を創るとき、
男性をトネリコから、
女性をエルムから
生み出したと伝えられています。
エルムは命を受け止め、
形を与える器のような存在——
生命をこの世に“とどまらせる木”として、
静かに支える力を象徴しています。
ローマのエルムが
「実りをもたらす木」なら、
北欧のエルムは
「存在を支える木」。
どちらも、二つの世界のあいだに立ち、
つなぐ役を担う木です。

オランダエルム病で
多くの木が失われた今も、
かつての美しい姿を
覚えている人は少なくありません。
風景の中で、人の営みを見守り、
風や雨に耐えながら
静かに大地に根を張ってきた木——
その姿は、
責任や使命を抱えて生きる
人の姿とどこかで響き合って
いるようです。
+ ————- +
10月26日(日)の読書会では、
ジュリアン・バーナード著
『バッチのフラワーレメディー 植物のかたちとはたらき』より、
「エルム」と「アスペン」を
読み進めます。
単発でもご参加いただけます。
どうぞこちらから詳細をご覧ください>>
読書会「セカンド19」
*第2回 10月26日(日)13:30~16:30(途中休憩あり)
p.181 第11章「後半のレメディの始まり」
チェリー・プラム、エルム、アスペン
□ 色、吸枝、根の役割と意味
p.201 第13章「人生との消極的な関わり」
チェストナット・バッド
□ 植物の成長